映画のDVDラベルを作っています。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
野菜の無人販売所に置いてある料金箱を見ると、日本はすごい国だなとあらためて感じます。写真は山梨県にあった無人販売所です。拙宅(八王子市)の近くにもいくつも販売所はありますが、たいてい料金箱は針金でくくり付けになっているブリキの缶であったり、売り場の棚や壁と一体になった木の箱であったりします。つまり、料金箱を持って行かれないような工夫をしてあるのが普通ですが、ここの販売所では金属の工具箱に硬貨を入れる穴が開いているだけで、どこにも固定せずに売り場にポンと置いてありました!もし、誰かに持って行かれたらどうするんだろう、と思わず考えてしまいました。
壁には「正直は一生の宝なり」と生真面目な綺麗な字で書いた貼り紙があります。きっとこれを見たお客さんはよもや悪いことをするまい、と見切りの利く親父さんが貼り付けたものに違いありません。もしかしたら、このお店のご主人は元小学校の校長先生で背筋をピンと伸ばして、習字のお手本通りにきちっとした丁寧な字を書く方かも知れませんね。
これを見て、やはり日本はすごい国だなあと感じます。大変大雑把な言い方ですが、これが他の国だったらどうなるだろうかと予想してしまいます。何でも盗られてしまう国だったら。
海外旅行が解禁されブームになっていた頃の笑い話ですが、イタリアで日本人観光客が三脚にセットしたカメラのセルフタイマーをかけてポーズする場所に走って戻ってカメラの方を見たら・・・すでにカメラは盗られてしまって無かった!というのがありました。
古来、陸続きの大陸にある国家は互いに侵略の歴史を繰り返して来たことが普通です。手に入るものは手に入れ、食べるものは食べてしまわないと、逆にいつ誰に盗られるか分からないからです。これが普遍的事実です。
例えば中国人は明日に取っておくと誰か盗られてしまうから、今日食べてしまう方が良い、という考え方でした。ところが、日本は島国であって近世まで侵略された経験が無かったので日本人の精神文化の形成に当たって大きな影響がありました。自分よりまず相手のことを考えても、異民族に侵略されることまでは無かったからです。日本こそ世界の秘境なんですね。

壁には「正直は一生の宝なり」と生真面目な綺麗な字で書いた貼り紙があります。きっとこれを見たお客さんはよもや悪いことをするまい、と見切りの利く親父さんが貼り付けたものに違いありません。もしかしたら、このお店のご主人は元小学校の校長先生で背筋をピンと伸ばして、習字のお手本通りにきちっとした丁寧な字を書く方かも知れませんね。
これを見て、やはり日本はすごい国だなあと感じます。大変大雑把な言い方ですが、これが他の国だったらどうなるだろうかと予想してしまいます。何でも盗られてしまう国だったら。
海外旅行が解禁されブームになっていた頃の笑い話ですが、イタリアで日本人観光客が三脚にセットしたカメラのセルフタイマーをかけてポーズする場所に走って戻ってカメラの方を見たら・・・すでにカメラは盗られてしまって無かった!というのがありました。
古来、陸続きの大陸にある国家は互いに侵略の歴史を繰り返して来たことが普通です。手に入るものは手に入れ、食べるものは食べてしまわないと、逆にいつ誰に盗られるか分からないからです。これが普遍的事実です。
例えば中国人は明日に取っておくと誰か盗られてしまうから、今日食べてしまう方が良い、という考え方でした。ところが、日本は島国であって近世まで侵略された経験が無かったので日本人の精神文化の形成に当たって大きな影響がありました。自分よりまず相手のことを考えても、異民族に侵略されることまでは無かったからです。日本こそ世界の秘境なんですね。
PR
昨日は東京西部の狭山丘陵にある多摩湖(村山貯水池)まで遠足に行って来ました。多摩センターから多摩モノレールに乗って終点の上北台駅まで行き、そこから歩きました。5月の五月晴れですので爽やかでしたが少し暑くなりました。
多摩湖と狭山湖(山口貯水池)はいずれも大正時代に着工され、昭和に入って竣工した人造湖です。きっかけは明治時代に東京でコレラが流行し上水道の整備が急務となったからです。
そう言えば、筆者が小学生の夏に東京では水不足があって、学校では先生が「皆さん、水は我慢してなるべく飲まないように! 飲むときも少しずつ飲むように!」と言い渡され、皆水道の蛇口に口を付けて一滴もこぼすまいと真剣になった記憶があります。でも、学校の校門を出たところのお蕎麦屋さんの店先では蕎麦屋の小父さんが「暑い!暑い!」と言いながらバケツと柄杓でジャブジャブと水を路上に撒いていたので、小学生たちは何てもったいないことをするんだろう、と皆で小父さんを睨みつけたものです。東京砂漠という言葉が出来たのもこの時だったようです。
また、思い出しましたが、この頃は小学校で栄養補助食品を配給(もちろん買うのですが)していました。何かというと「肝油(かんゆ)ドロップ」です。後から調べたらタラやその他浮き袋を持たない深海魚が浮力を得るために油を蓄えるのですが、これに日本的に甘い味を付けて大ヒットしました。今から考えると不思議な味でしたが、皆栄養補給に熱心な時代だったように思います。現在でも売られているようですね。
筆者は高校時代に全校マラソン大会で訪れて以来の多摩湖周辺でした。貯水池の優美なデザインの給水塔を見てあらためて当時の記憶を思い出しました。
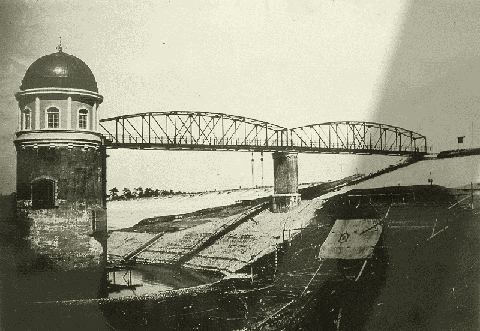
多摩湖と狭山湖(山口貯水池)はいずれも大正時代に着工され、昭和に入って竣工した人造湖です。きっかけは明治時代に東京でコレラが流行し上水道の整備が急務となったからです。
そう言えば、筆者が小学生の夏に東京では水不足があって、学校では先生が「皆さん、水は我慢してなるべく飲まないように! 飲むときも少しずつ飲むように!」と言い渡され、皆水道の蛇口に口を付けて一滴もこぼすまいと真剣になった記憶があります。でも、学校の校門を出たところのお蕎麦屋さんの店先では蕎麦屋の小父さんが「暑い!暑い!」と言いながらバケツと柄杓でジャブジャブと水を路上に撒いていたので、小学生たちは何てもったいないことをするんだろう、と皆で小父さんを睨みつけたものです。東京砂漠という言葉が出来たのもこの時だったようです。
また、思い出しましたが、この頃は小学校で栄養補助食品を配給(もちろん買うのですが)していました。何かというと「肝油(かんゆ)ドロップ」です。後から調べたらタラやその他浮き袋を持たない深海魚が浮力を得るために油を蓄えるのですが、これに日本的に甘い味を付けて大ヒットしました。今から考えると不思議な味でしたが、皆栄養補給に熱心な時代だったように思います。現在でも売られているようですね。
筆者は高校時代に全校マラソン大会で訪れて以来の多摩湖周辺でした。貯水池の優美なデザインの給水塔を見てあらためて当時の記憶を思い出しました。
以前、山の主食はオニギリかパンかという話題を書きましたが、副食として欠かせないのが魚肉ソーセージです。安くて保存が利き、すぐに食べられるということもあって、思い起こせば中学生時代のサイクリングの頃から貴重な食糧品だったように思います。
初めて食べるときは肉から作ったソーセージだと思っていました。唯一の難点は製品によってビニールの包装がきれいに剥けるかどうかということはあるのですが、今でもなぜか山に持って行って食べたい食糧の一つですね。
肉のソーセージならぬ魚肉で作ったソーセージは日本的コピー食品の王者かも。それで思い出しましたが、昔、僕らが小学生だったころ、「人造肉」というのがありました。小麦・大豆などの植物タンパクから作ったものという記憶があります。これももう40年も前の話ですが、小学校の理科の先生が「ついに人造肉が出来ました!」と興奮していたのを思い出しました。
ついでに思い出しましたが、林間学校でキャンプファイヤーを囲んで「これから三十一年たてばこのは二十一世紀・・・」という歌を皆で歌ったのを思い出しました。当時の小学生にはまったく何も想像もできませんでしたが。とっくに21世紀になりましたが、世の中全然良くならないですね。
先日、ネットで検索したら、現代は最先端の科学培養技術で人造肉が作れるようです。幸いにもまだホンモノの肉が売られている時代で良かったで。前述の歌は佐良直美のヒット曲でした。

初めて食べるときは肉から作ったソーセージだと思っていました。唯一の難点は製品によってビニールの包装がきれいに剥けるかどうかということはあるのですが、今でもなぜか山に持って行って食べたい食糧の一つですね。
肉のソーセージならぬ魚肉で作ったソーセージは日本的コピー食品の王者かも。それで思い出しましたが、昔、僕らが小学生だったころ、「人造肉」というのがありました。小麦・大豆などの植物タンパクから作ったものという記憶があります。これももう40年も前の話ですが、小学校の理科の先生が「ついに人造肉が出来ました!」と興奮していたのを思い出しました。
ついでに思い出しましたが、林間学校でキャンプファイヤーを囲んで「これから三十一年たてばこのは二十一世紀・・・」という歌を皆で歌ったのを思い出しました。当時の小学生にはまったく何も想像もできませんでしたが。とっくに21世紀になりましたが、世の中全然良くならないですね。
先日、ネットで検索したら、現代は最先端の科学培養技術で人造肉が作れるようです。幸いにもまだホンモノの肉が売られている時代で良かったで。前述の歌は佐良直美のヒット曲でした。
町田市小山にある蚕種石(こだねいし)を見て来ました。何でも今から二千八百年前からある石で小字としての地名でもあったそうです。
石の由来はちょっと神がかった説明でしたが、昔の人は初夏八十八夜にこの石が緑色に変わるのを見て、農作業の時期を知ったようです。石に対する信仰は神社などが出来るよりずっと以前からの原始的な信仰の形態だそうです。
すぐ近くでは写真の大きな屋根の家屋敷を見かけました。おそらくは昔の藁葺き屋根に上を被せたものと思います。周辺の入り組んだ細い小道は昔からの集落であることが分かります。この辺は養蚕が盛んだったと聞いています。
今日も朝から暑かったですが新しい発見がありました。暑い中での散歩もまた一興、というのは痩せ我慢でしょうか?


石の由来はちょっと神がかった説明でしたが、昔の人は初夏八十八夜にこの石が緑色に変わるのを見て、農作業の時期を知ったようです。石に対する信仰は神社などが出来るよりずっと以前からの原始的な信仰の形態だそうです。
すぐ近くでは写真の大きな屋根の家屋敷を見かけました。おそらくは昔の藁葺き屋根に上を被せたものと思います。周辺の入り組んだ細い小道は昔からの集落であることが分かります。この辺は養蚕が盛んだったと聞いています。
今日も朝から暑かったですが新しい発見がありました。暑い中での散歩もまた一興、というのは痩せ我慢でしょうか?
写真は何だと思いますか?昨日、道端で摘んできたノビルを鉢に植えたものです。一見美味しそうな野菜に見えませんか。今後の食糧難に備え、食べられる雑草を集めてみようかと思っています。
昨日、ボール紙を食ったような味という話を書きました。これはまあ、見かけより意外な味がしたという話で食べ物の美味い不味いの範疇です。
一方、人間は所属する生活圏の食習慣に抵抗のある食べ物は自己防衛の本能から生理的嫌悪感を催して、それを口にすることが出来ません。意志で乗り越えて口にしても吐き出すことが多いです。
以前、テレビ番組であるタレントが生きたイモムシをパクパク食べるのを見て、かなり一般的日本人と違う感覚を持った方だと思いました。また、だいぶ昔ですが奇人変人を紹介する番組で、明らかにテレビに出たいがために、台所にいる昆虫を御飯に乗せて食べて見せた少年がいて、その後の噂ではお腹を虫に食い荒らされて死んでしまったなどと噂されたものです。
思い出すのは番組司会者の土居まさるが「君、もう止めなさい!」と生理的嫌悪感から思わず叫んだことですね。
小生は中国へ旅行した際にバーベキューの店でクシに刺したニワトリの頭と、蚕のサナギを食べたことです。ニワトリの頭は食べられましたが、虫のサナギは日本でも食べた経験がなく、最初は一目見て絶対無理だと思いましたが、何とか一つ食べてみました。味はセメントを食ったような味でした。(セメントを食ったことはありませんけど。)
思わず吐き出ししそうな気持ちを抑えて飲み込みましたが、あの味と食感は忘れられない強烈な思い出となって残っています。

昨日、ボール紙を食ったような味という話を書きました。これはまあ、見かけより意外な味がしたという話で食べ物の美味い不味いの範疇です。
一方、人間は所属する生活圏の食習慣に抵抗のある食べ物は自己防衛の本能から生理的嫌悪感を催して、それを口にすることが出来ません。意志で乗り越えて口にしても吐き出すことが多いです。
以前、テレビ番組であるタレントが生きたイモムシをパクパク食べるのを見て、かなり一般的日本人と違う感覚を持った方だと思いました。また、だいぶ昔ですが奇人変人を紹介する番組で、明らかにテレビに出たいがために、台所にいる昆虫を御飯に乗せて食べて見せた少年がいて、その後の噂ではお腹を虫に食い荒らされて死んでしまったなどと噂されたものです。
思い出すのは番組司会者の土居まさるが「君、もう止めなさい!」と生理的嫌悪感から思わず叫んだことですね。
小生は中国へ旅行した際にバーベキューの店でクシに刺したニワトリの頭と、蚕のサナギを食べたことです。ニワトリの頭は食べられましたが、虫のサナギは日本でも食べた経験がなく、最初は一目見て絶対無理だと思いましたが、何とか一つ食べてみました。味はセメントを食ったような味でした。(セメントを食ったことはありませんけど。)
思わず吐き出ししそうな気持ちを抑えて飲み込みましたが、あの味と食感は忘れられない強烈な思い出となって残っています。
庭のグラパラの花が咲きました。知り合いの方からいただいてすぐ、葉っぱの一枚を食べてみましたが、あまり味がしなかったです。外国でよく食べられ、最近は日本のスーパーでも売っているそうですが、何も味付けをしないと我々日本人は一般的にダメですね。
本多勝一氏の紀行文を読むと、例えばニューギニアの高地に住む民族が美味しそうに食べているバナナを試しに食べてみたら、ボール紙を煮て食っているような味だったとか、エスキモーが穫ったその場で生肉にかぶり付くのはあくまで生食であって料理ではない、生肉であっても調味料を付ければ了解な料理であると書いてあります。
要するに人間の味覚はかなりいい加減なもので、与えられた条件下の比較では美味い不味いはあっても、民族の生活環境としてはそこで食するものが一番美味いと思い込んでいるという話です。
サラダに使う野菜は沢山あるので、もしグラパラが繁殖して毎日食べても大丈夫な量になったとしたら、果たしてグラパラを食べているでしょうか?貴方もぜひお試しください。

本多勝一氏の紀行文を読むと、例えばニューギニアの高地に住む民族が美味しそうに食べているバナナを試しに食べてみたら、ボール紙を煮て食っているような味だったとか、エスキモーが穫ったその場で生肉にかぶり付くのはあくまで生食であって料理ではない、生肉であっても調味料を付ければ了解な料理であると書いてあります。
要するに人間の味覚はかなりいい加減なもので、与えられた条件下の比較では美味い不味いはあっても、民族の生活環境としてはそこで食するものが一番美味いと思い込んでいるという話です。
サラダに使う野菜は沢山あるので、もしグラパラが繁殖して毎日食べても大丈夫な量になったとしたら、果たしてグラパラを食べているでしょうか?貴方もぜひお試しください。
小山田を歩く、と言いながら実際には自転車で走っているのですが、気分はウォーキングです。
小山田という地名には思い入れがあって、戦国時代の甲斐の武田信玄に仕えた郡内の領主に小山田信茂という勇将がいました。この人は信玄に仕えて数知れず軍功を立てましたが、武田家滅亡の際には末期を汚して主君を裏切り、纓田信忠に投稿したものの、信忠から主君への不忠を免罵され、織田家により斬首されました。
前置きが長くなりましたが、小山田は平安鎌倉の頃から土着の土豪であった小山田氏の祖によって開墾されました。小山田どころか町田一帯はすべて小山田氏の領地だったようですね。
領主の舘があったところには、今は大泉寺というお寺が残ります。このお寺の山門が実に立派で、小山田氏の記憶と相まって遠く戦国時代の昔に迷いこんだような錯覚を覚えます。ここに来る度に写真を撮ってしまいます。
小山田緑地にはアサザ池という池とも言えない湿地があります。今日はここまで散歩に来ました。




小山田という地名には思い入れがあって、戦国時代の甲斐の武田信玄に仕えた郡内の領主に小山田信茂という勇将がいました。この人は信玄に仕えて数知れず軍功を立てましたが、武田家滅亡の際には末期を汚して主君を裏切り、纓田信忠に投稿したものの、信忠から主君への不忠を免罵され、織田家により斬首されました。
前置きが長くなりましたが、小山田は平安鎌倉の頃から土着の土豪であった小山田氏の祖によって開墾されました。小山田どころか町田一帯はすべて小山田氏の領地だったようですね。
領主の舘があったところには、今は大泉寺というお寺が残ります。このお寺の山門が実に立派で、小山田氏の記憶と相まって遠く戦国時代の昔に迷いこんだような錯覚を覚えます。ここに来る度に写真を撮ってしまいます。
小山田緑地にはアサザ池という池とも言えない湿地があります。今日はここまで散歩に来ました。
昨日、花屋さんでネモフィラとバコパを買って来ました。どちらも小さな花を沢山咲かせます。前にも育てたことがあります。
ネモフィラはどこかの大きな公園にあるように群生すると大変見事ですが、美しいブルーはコスモスと同じく北アメリカ原産で、いかにも北アメリカに分布する花のようなイメージです。コスモスのように丈は高くなりませんが、やや長く這うように延びます。
バコパは別名ステラと言って、こちらはアフリカ原産で立ち上がらずに地面に広がりますので管理が楽ですね。小さな花が一面に広がります。
バコパは地味な小さな花なので寄せ植えの付け合わせみたいですが、植木鉢いっぱいに丸く広がると見応えがありますね。
どちらも春から出回ってやや値段も下がっているので100円程度で安く買えました。高い美しい花を買うより、地味な小さな花を大切に育てて綺麗に咲かせたいと思っています。

ネモフィラはどこかの大きな公園にあるように群生すると大変見事ですが、美しいブルーはコスモスと同じく北アメリカ原産で、いかにも北アメリカに分布する花のようなイメージです。コスモスのように丈は高くなりませんが、やや長く這うように延びます。
バコパは別名ステラと言って、こちらはアフリカ原産で立ち上がらずに地面に広がりますので管理が楽ですね。小さな花が一面に広がります。
バコパは地味な小さな花なので寄せ植えの付け合わせみたいですが、植木鉢いっぱいに丸く広がると見応えがありますね。
どちらも春から出回ってやや値段も下がっているので100円程度で安く買えました。高い美しい花を買うより、地味な小さな花を大切に育てて綺麗に咲かせたいと思っています。
今日、花屋さんでモッコウバラを見たら500円に値下がりしていました。最初に店頭で見たときは1000円以上でしたけど。店頭で売っている丸い支柱に沿わせた作りは、行灯(あんどん)仕立てと言うそうです。
先日も書きましたが、モッコウバラは上品な黄色の小さな花が咲き、僕の最も好きな花の一つです。我が家の庭にもウッドデッキの垣根に這わせてあります。
今日は昨年咲いたクンシランのタネを取り出して洗いました。クンシランは株分けで増やすことが多いのですが、タネを植えて増やすことも出来ます。赤い実が十分熟すのを待って中を開くと大きなタネを取り出し、水洗いします。これを土に植えるのですが、芽が出るまでにかなりの時間がかかります。
今年は初めて黄色のクンシランが咲きました。オレンジ色のクンシランと並べておくと、色の対比が抜群に美しくお勧めです。
黄色のクンシランのタネを採って友人達や知り合いの方にお分けすることが、今後の楽しみです。



先日も書きましたが、モッコウバラは上品な黄色の小さな花が咲き、僕の最も好きな花の一つです。我が家の庭にもウッドデッキの垣根に這わせてあります。
今日は昨年咲いたクンシランのタネを取り出して洗いました。クンシランは株分けで増やすことが多いのですが、タネを植えて増やすことも出来ます。赤い実が十分熟すのを待って中を開くと大きなタネを取り出し、水洗いします。これを土に植えるのですが、芽が出るまでにかなりの時間がかかります。
今年は初めて黄色のクンシランが咲きました。オレンジ色のクンシランと並べておくと、色の対比が抜群に美しくお勧めです。
黄色のクンシランのタネを採って友人達や知り合いの方にお分けすることが、今後の楽しみです。
先日、実家の母親に秋田の桜皮細工の箸を貰って来ました。
だいぶ前に両親が秋田の角館へ旅行した際に買い求めたものだそうです。美しいサクラの皮が張られていて日用としては惜しくて使えなかったとのことでした。
桜皮細工は江戸時代以来の伝統があり、この箸の木は白南天だそうです。使いなさいと貰ったものの、父親の形見でもあるこの箸をおろして使ってしまっていいのか、ちょっと考えています。
司馬遼太郎氏の「菊一文字」に、沖田総司がぞっこん惚れ込んだ借り物の名刀を惜しむくだりがあります。ふと、それを思い出しました。沖田の父親は奥州白河脱藩だったようです。江戸時代の庶民は、桜皮細工の日用品などはたして使ったのでしょうか。

先日、実家の母親に秋田の桜皮細工の箸を貰って来ました。
だいぶ前に両親が秋田の角館へ旅行した際に買い求めたものだそうです。美しいサクラの皮が張られていて日用としては惜しくて使えなかったとのことでした。
桜皮細工は江戸時代以来の伝統があり、この箸の木は白南天だそうです。使いなさいと貰ったものの、父親の形見でもあるこの箸をおろして使ってしまっていいのか、ちょっと考えています。
司馬遼太郎氏の「菊一文字」に沖田総司が借り物でぞっこん惚れ込んだ借り物の名刀を惜しむくだりがあります。ふと、それを思い出しました。沖田の父親は奥州白川浪人だったようです。江戸時代の庶民は、桜皮細工の日用
品などはたして使ったのでしょうか。

だいぶ前に両親が秋田の角館へ旅行した際に買い求めたものだそうです。美しいサクラの皮が張られていて日用としては惜しくて使えなかったとのことでした。
桜皮細工は江戸時代以来の伝統があり、この箸の木は白南天だそうです。使いなさいと貰ったものの、父親の形見でもあるこの箸をおろして使ってしまっていいのか、ちょっと考えています。
司馬遼太郎氏の「菊一文字」に沖田総司が借り物でぞっこん惚れ込んだ借り物の名刀を惜しむくだりがあります。ふと、それを思い出しました。沖田の父親は奥州白川浪人だったようです。江戸時代の庶民は、桜皮細工の日用
品などはたして使ったのでしょうか。
昨日は久しぶりのハイキングで笹子山塊を歩きました。今日は起きたら、身体がガタガタです。全身疲労でたぶん筋肉は乳酸でいっぱいです。
なにしろ季節はずれの暑さで稜線で23度、笹子の甲州街道で26度の暑さでしたが、それでも風があって助かりました。
未だ新緑というには早いのですが、目にも鮮やかな木々の若葉をたっぷり記憶に焼きつけて来ました。
この辺の山は訪れる人も多くなく、静かな山歩きが楽しめます。フィトンチッド溢れる広葉樹林帯の森が好きなので1000~1500mの山が一番行きたい場所です。
ハイキングは一年中歩くので春がシーズンの初めではないですが、若葉、ヤマザクラ、ミツバツツジの組み合わせを見るとき、今年も沢山山へ登ろうと心新たに思います。



なにしろ季節はずれの暑さで稜線で23度、笹子の甲州街道で26度の暑さでしたが、それでも風があって助かりました。
未だ新緑というには早いのですが、目にも鮮やかな木々の若葉をたっぷり記憶に焼きつけて来ました。
この辺の山は訪れる人も多くなく、静かな山歩きが楽しめます。フィトンチッド溢れる広葉樹林帯の森が好きなので1000~1500mの山が一番行きたい場所です。
ハイキングは一年中歩くので春がシーズンの初めではないですが、若葉、ヤマザクラ、ミツバツツジの組み合わせを見るとき、今年も沢山山へ登ろうと心新たに思います。
最新記事
(09/12)
(09/11)
(09/10)
(09/09)
(09/08)
(09/07)
(09/06)
(09/05)
(09/04)
(09/03)
リンク
amazonベストセラー
amazon市場
楽天市場
Amazonライブリンク





